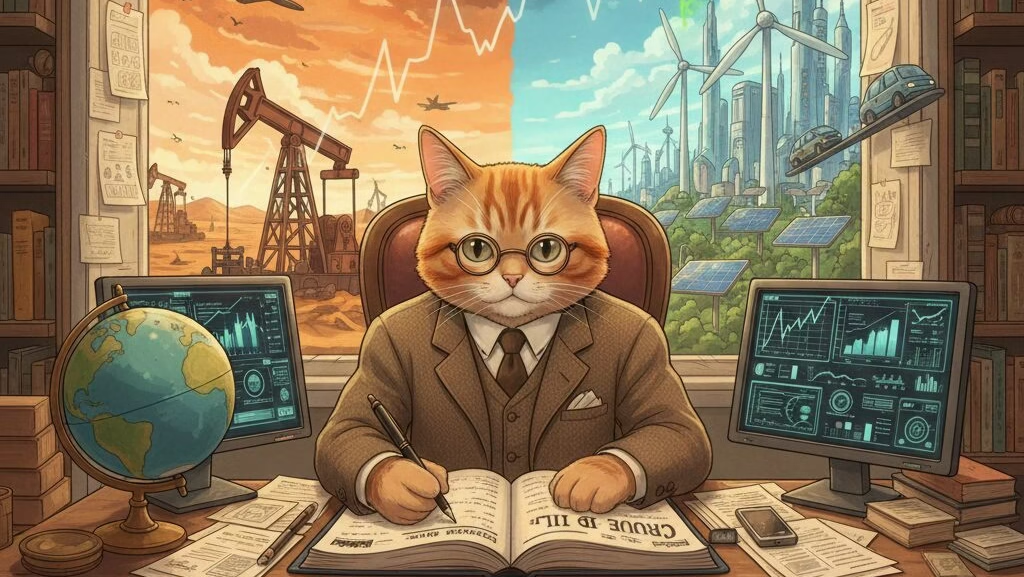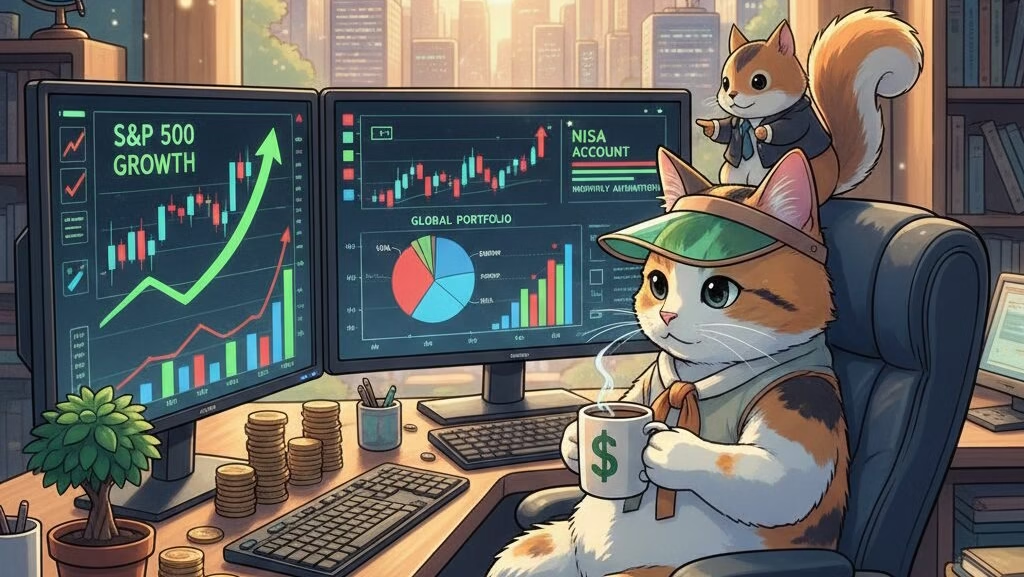r>g:資本主義の残酷な真理


おつかれさまです。ためネコです🐱
今回のテーマは”r>g:資本主義の残酷な真理”です。
資本主義の本質を露わにした有名な不等式ですが、いかに”r”を高めるかが、蓄財のカギとなります。
現代の資本主義社会を理解し、個人が富を築く上で避けて通れないのが、「r > g」という有名な不等式です。この論理を理解し、自身の経済戦略に活かすことこそが、蓄財の鍵となります。
資本主義の「宿命」:r > gの不等式
「r > g」は、フランスの経済学者トマ・ピケティがその著書『21世紀の資本』で、歴史的な膨大なデータを分析して明らかにした資本主義社会の基本的な傾向を示すものです。
r:資本収益率とは
rは、資本収益率(Rate of return on capital)を指します。具体的には、株式、債券、不動産などの資産(資本)を運用することで得られる収益の割合です。配当、利息、賃料、キャピタルゲインなどがこれに含まれます。歴史的な長期平均で見ると、このrは概ね5%程度で推移してきたとされています。
g:経済成長率とは
一方のgは、経済成長率(Rate of growth)を指します。これは、社会全体の成長スピードのことで、主に労働所得の伸びやGDPの成長率に相当します。技術革新や人口増加などによって決まる要素が大きく、歴史的な長期平均では2%以下で推移する傾向があります。
不等式が示すもの
r > gという不等式が成り立つということは、資産から得られる収益の増加率が、労働によって得られる所得の増加率を恒常的に上回ることを意味します。
簡単に言えば、働いて得るお給料よりも、資産を運用して得るお金の方が、より速いペースで増えていくということです。
格差の拡大メカニズム
この「r > g」こそが、資本主義社会における富の集中と格差拡大の根源的メカニズムであるとピケティは指摘しました。
資産を持つ者の優位性
既に一定の資本(資産)を持つ者は、その資産を投資に回すことで「r」の恩恵を受け続けられます。資本が雪だるま式に増えていく複利効果が働き、その富は加速的に増加します。その増加ペースは、社会全体の平均的な賃金上昇率(g)を上回るため、時間が経つにつれて、資産を持つ者と持たざる者の間の経済格差は広がる一方となります。
労働所得中心の限界
労働所得(給与)を中心に生活している人々にとって、収入の伸びは「g」に限定されます。いくら懸命に働いても、その所得の伸びは「r」のペースに追いつくことは困難です。結果として、真面目に働くだけでは、資本の力によって富を増やしていく人々との差は開く一方、という現実が生まれてしまうのです。
この構造は、努力や才能といった個人の属性を超えて、資本の有無が個人の経済的な成功を大きく左右することを示しています。
蓄財戦略:rをいかに高めるか
「r > g」が資本主義の宿命であるならば、個人が蓄財を成功させる、つまり経済的な自由を得るための戦略は自ずと見えてきます。それは、自分自身を「r」の側に置くことに尽きます。
1. 労働所得の一部を資本へ変える
最初のステップは、現在の労働所得をただ消費するか貯蓄(預金など、低リターンなもの)するだけでなく、積極的に「資本」へと変えていくことです。これが投資です。少額であっても、株式、インデックスファンド、不動産といった高い資本収益率(r)が期待できる資産へ回すことが重要です。
2. 時間の力を味方につける
投資によって得られた収益を再投資し、複利効果を最大限に活用することが「r」を高める本質です。複利効果は、運用期間が長くなるほど強力になるため、若いうちから、あるいは少額でも良いので、長期的に積立投資を続けることが、rの恩恵を享受する上で極めて重要になります。時間を味方につけることで、資産は指数関数的に増加しやすくなります。
3. 税制優遇制度の活用
NISAやiDeCoといった税制優遇制度は、運用益にかかる税金を非課税にするなど、実質的なrを効率的に高めるための強力なツールです。これらを最大限に活用することは、労働所得から資本所得への移行を後押しし、蓄財のスピードを加速させます。
「r > g」は、格差の拡大を嘆くための論理であると同時に、私たち個人が資本主義社会で豊かになるための羅針盤でもあります。この真実を理解し、「働く力(g)」で種銭を作り、「資本の力(r)」でその富を育むサイクルを確立することこそが、現代における最も確実な蓄財戦略と言えるでしょう。

本業・副業・投資・節約(節税)のサイクルをうまく回して、経済的自由(多様な選択肢)を目指いしたいですね。
それでは、また🐱